広告効果を最大化する!Google広告の入札戦略の種類と選び方ガイド

皆さんは、広告の入札戦略についてどこまでご存じでしょうか?目的や目標により、様々な入札戦略があります。Google広告で効果的に広告を配信するには、入札戦略の設定が重要です。そこで今回は、Google広告の入札戦略について詳しく説明していきたいと思います。
目次
入札戦略とは?

入札戦略とは、広告のオークションにおいて広告の入札価格を決める方法のことです。広告の表示は、ユーザーが検索するたびに実施されるオークションによって決まり、広告ランクが一定以上のものが掲載されます。
広告の目的や予算に応じて最適な入札価格を設定することで、広告の効果を最大化することができます。そして、Google広告では「手動入札」と「自動入札」の2種類の入札方法があります。
手動入札とは?
広告主が自分で入札価格を設定する方法です。キーワードごとに最大入札額を自由に調整できるため、広告費用を細かく管理できます。
特に、クリック単価やコンバージョン率を詳細に分析しながら効率化したい場合に手動入札は効果的な手法です。
自動入札とは?
Googleが広告主の目標に基づいて自動的に入札価格を調整する方法です。広告主が個別に入札額を設定する必要がなく、Googleがリアルタイムでデータを分析し、より高い成果が期待できるユーザーに対して適切な入札を行います。
広告主は運用の手間を省きながら、広告の効果を最大化することができます。
手動入札の目的別の種類や特徴

個別クリック単価制
個別クリック単価制は、クリック数の最大化を目的とする入札戦略です。広告がクリックされたときのみ料金が発生する仕組みで、広告主が上限金額を設定でき、広告のクリック数に応じて料金を支払います。また、上限クリック単価を超える金額は請求されません。
個別クリック単価制のメリット
予算を細かく制御できる
キーワードや広告ごとに入札額を細かく設定できるため、予算の管理がしやすく無駄なコストを抑えられます。特に、予算が限られている場合や特定の指標目標を重視する場合に最適です。
詳細なコントロールが可能
広告の配信スケジュールや掲載順位、ターゲットユーザー層ごとに細かい調整が可能です。競争が激しいキーワードでは、掲載順位を考慮しながら入札額を調整できるため、無駄なコストを抑えつつ狙ったターゲットに最適な形で広告を届けることができます。
個別クリック単価制のデメリット
入札調整の管理コストが非常にかかる
キーワードごとに入札額を細かく設定できる反面、管理の手間が大きいです。特に広告の効果を最大化するためには、競合の入札状況やクリック単価、コンバージョン率を常に分析し、適切な調整を行う必要があります。さらに、広告スケジュールやデバイス別、地域別の入札調整も手動で管理する必要があるため、運用リソースが限られている場合は負担が大きくなりやすいです。
拡張クリック単価
拡張クリック単価は、コンバージョン獲得を目的とする入札戦略です。手動で設定した入札価格を基にGoogleが自動で調整を行う機能です。コンバージョンの可能性が高いクリックには入札額引上げ、低い場合は引き下げることでコストを抑えながらコンバージョンの最大化を目指します。手動入札の自由度を保ちつつ、自動最適化のメリットも得られるため完全な自動入札に抵抗がある場合に適した戦略です。
拡張クリック単価のメリット
完全な自動入札に比べてコントロールしやすい
手動入札の自由度を維持しながら、Googleの機械学習を活用して最適化できるのが特徴です。完全な自動入札とは異なり、広告主が入札額をある程度コントロールできるため調整の柔軟性が高いです。自動化のメリットも取り入れつつ、手動管理の安心感も得られるため自動入札に不安がある場合でも使いやすい入札戦略になります。
管理負担を軽減できる
手動入札のように細かく調整する必要がなく、自動で最適な入札額に調整されるため管理負担を軽減できます。完全な手動入札に比べパフォーマンス向上のための入札調整の手間が少なくなるのがメリットです。自動化の恩恵を受けながらも、手動入札のコントロールを一部維持できるため、運用の効率化と成果の向上を両立しやすいです。
拡張クリック単価のデメリット
入札単価が想定より高くなる可能性がある
コンバージョンの可能性が高いと判断された場合に自動で入札額を引き上げるため、想定以上にクリック単価が上昇することがあります。その結果、広告費が増え予算を超えてしまうリスクがある点に注意が必要です。手動に比べ、入札単価のコントロールが難しくなるため定期的なモニタリングが欠かせません。
インプレッション単価制
インプレッション単価制は、インプレッション数の最大化を目的とする入札戦略です。広告の表示回数に応じて料金が発生する仕組みで、クリック数ではなく広告の露出回数を重視するためブランド認知度向上に効果的です。特に、多くのユーザーに広告を見てもらいたい場合に適しており、ディスプレイ広告や動画広告で活用されます。
インプレッション単価制のメリット
ブランド認知度を向上させやすい
クリック数に関係なく広告が表示されるため、多くのユーザーにリーチできるのが特徴です。広告の露出を増やすことで、ブランドの認知度を高めやすく新規顧客へのアプローチにも効果的です。特に視覚的なインパクトの強いディスプレイ広告や動画広告との相性が良い入札戦略です。
クリック率を気にせず運用できる
インプレッション単価制は、クリック数ではなく広告の表示回数に基づいて課金されるため、クリック率を気にせず運用できます。クリック率が低くても広告を大量に露出できるため、視認性を重視したキャンペーンに適しており、ブランド認知を目的としたディスプレイ広告や動画広告で効果を発揮します。
インプレッション単価制のデメリット
効果測定が難しい
表示回数が主な指標となるため、クリック率やコンバージョンの測定が難しいのがデメリットです。広告が多くて表示されても、実際にどれだけのユーザーが関心を持ったのか判断しにくいことがあります。ブランド認知度向上には効果的ですが、直接的な売上や成果を測るのには適しておりません。
視認範囲のインプレッション単価制
視認範囲のインプレッション単価制は、インプレッション数の最大化を目的とする入札戦略です。ディスプレイ広告において、ユーザーに広告が視認された場合のみ課金される入札戦略です。広告の認知度向上を目的としており、クリック数やサイト訪問数の増加ではなく、視認性を高めることに重点を置いた運用に適しています。ブランドの露出を最大化したい場合に効果的な手法です。
視認範囲のインプレッション単価制のメリット
無駄なコストを抑え、視認性を重視した広告配信が可能
ユーザーがスクリーン上で一定時間広告を視認した場合にのみ課金されるため、無駄なコストを抑えられます。通常の表示回数課金とは異なり、スクロールなどで実際に見られなかった広告には課金されないのが特徴です。これにより、より効果的な広告配信が可能となり、ブランド認知度の向上に貢献します。
視認性を重視する広告キャンペーンに最適
広告の視認性を最優先するキャンペーンに最適です。クリック数やコンバージョンではなく、ユーザーに広告がしっかりと認識されることを重視したブランドプロモーション向けの手法です。これにより、広告の露出効果を最大化し認知度向上に貢献します。
視認範囲のインプレッション単価制のデメリット
クリック課金と比較して費用対効果が低い場合がある
クリックが発生しなくても課金されるため、費用対効果が低くなる場合があります。特に、サイト訪問や購入などの直接的なアクションを目的とする広告には不向きです。クリック課金と比較すると、ユーザーの関心度に関係なく費用が発生するため、目的に応じた使い分けが重要です。
自動入札の目的別の種類や特徴
目標コンバージョン単価
目標コンバージョン単価は、限られた予算の中で出来るだけ多くのコンバージョンを獲得したい場合に適した自動入札戦略です。一件あたりのコンバージョン獲得単価の目標を設定することで、その範囲内で成果を最大化するようGoogleが自動で入札を最適化します。媒体によっては「コンバージョン数の最大化(目標コンバージョン単価の設定あり)」という表現もありますが、基本的には同じ戦略として扱われています。
目標コンバージョン単価のメリット
コンバージョン数を効率的に増やせる
設定した1件あたりの獲得単価を保ちながら、できるだけ多くのコンバージョンを獲得できるよう自動で入札が最適化される戦略です。限られた予算内で成果を最大化したい場合に有効で、費用対効果の高い運用が可能になります。手動での入札調整が不要なため、運用の手間を減らしつつ安定した成果が期待できます。
運用の手間を削減できる
入札単価の調整をGoogleが自動で行ってくれるため、手動での細かな管理が不要になります。これにより、日々の入札調整にかかる時間や手間を大幅に削減でき、運用効率が向上します。特に運用リソースが限られている場合でも、成果を維持しながらスムーズに広告配信が可能です。
目標コンバージョン単価のデメリット
手動での細かなコントロールがしにくい
Googleの自動最適化によって入札が調整されるため、手動での細かいコントロールが難しくなります。特定のキーワードや曜日、時間帯、デバイスごとに個別に入札を調整したい場合には柔軟性に欠けることがあります。より細かい戦略を立てたい広告主にとっては不向きな面もある入札方法です。
コンバージョン値の最大化
コンバージョン値の最大化は、設定した予算内で得られるコンバージョンの「価値(売上や成果)」を最大化することを目的とした入札戦略です。単なるコンバージョン数ではなく、1件ごとの成果の大きさを重視するため、ECサイトなどでの商品販売に特に効果的です。高単価商品や購入金額にばらつきがある商材に向いています。
コンバージョン値の最大化のメリット
売上や利益を最大化しやすい
単なる件数ではなくコンバージョンの価値に基づいて入札が最適化されるため、売上や利益の向上を目指しやすい入札戦略です。特に、高単価商品を購入する可能性の高いユーザーに優先的に広告を表示することで、収益性の高い成果を狙えます。これにより、限られた予算でも全体の売上を最大化しやすくなるのが特徴です。
ECサイトや有料サービスに最適
商品やサービスごとにコンバージョンの価値が異なるECサイトや有料サービスに最適な入札戦略です。金額の高い購入や契約に対して優先的な広告を配信できるため、より効率的な売上向上が期待できます。価値に応じた最適化により、広告費を有効に使えるのが大きなメリットです。
コンバージョン値の最大化のデメリット
コンバージョン値の正確な設定が必要
コンバージョン値の最大化を効果的に運用するには、各コンバージョンに対する正確な価値(売上や利益など)を設定する必要があり、この値が適切でないと、広告配信の最適化がうまく機能せず、狙った成果が出にくくなる可能性があります。特に複数の商品やサービスを扱う場合は、細かな設定と管理が求められます。
クリック数の最大化
クリック数の最大化は、Google広告やYahoo!広告などの検索広告で、設定した予算内でできるだけ多くのクリックを獲得することを目的とした入札戦略です。システムが自動的に入札単価を調整し、より多くのユーザーをウェブサイトへの誘導することを重視しています。特に、トラフィックの増加を目的としたキャンペーンに適しています。
クリック数の最大化のメリット
認知拡大やユーザー獲得に効果的
より多くのユーザーに広告をクリックしてもらうことを目的としているため、認知拡大に効果的です。広告の表示だけでなく実際の訪問を増やせるため、商品やサービスを広く知ってもらいたい場合に向いています。特に、新商品の告知やキャンペーンの周知など、初期段階のプロモーションに適した入札戦略です。
短期間でのテストにも向いている
短期間で多くのトラフィックを集められるため、新しい広告やLP(ランディングページ)の効果検証に最適です。すばやくデータを集められるため、改善点の発見やABテストなどにも活用しやすい戦略になります。初期段階の施策やテスト目的のキャンペーンにおすすめです。
クリック数の最大化のデメリット
コンバージョンにつながらないクリックが増える可能性がある
あくまでクリック数の増加を目的としているため、コンバージョンにつながらないクリックが発生することがあります。商品購入や問い合わせなどの成果を重視する場合、無駄なクリックによって費用がかさむ可能性があります。そのため、成果ベースの運用をしたい場合には注意が必要です。
目標インプレッションシェア
目標インプレッションシェアは、インプレッション数の最大化を目的とした入札戦略です。広告が表示された回数(インプレッション数)を表示可能だった最大回数で割って算出されます。この最大回数は、当日の広告オークションに基づき、ターゲティング設定、広告の承認状況、品質スコアなど複数の要因を考慮して決定されます。
目標インプレッションシェアのメリット
競合より上位に表示しやすい
目標インプレッションシェアは、検索結果の「最上部」や「ページ上部」など、広告を表示したい位置を指定できます。これにより、競合他社よりも上位かつ目立つ位置に広告を掲載しやすいです。ユーザーの目に留まりやすいため、クリック率や認知度の向上にもつながります。
自社ブランド名や指名キーワードを守れる
目標インプレッションシェアを活用することで、自社ブランド名や指名キーワードで検索された際に、広告を確実に表示させることができます。これにより、検索結果で競合の広告が上位に表示されるリスクを抑え、ユーザーを逃しにくくなります。ブランド保護の観点からも、指名検索の広告配信を安定させたい場合に有効な戦略です。
目標インプレッションシェアのデメリット
コストが高くなりやすい
検索結果の上位表示や高い表示シェアを目指すため、入札単価が自動的に高く設定されることがあります。その結果、広告費が想定以上に増える可能性があり、コスト効率が悪化することもあります。特に、競合が多いキーワードでは、費用が大きく膨らむリスクに注意が必要です。
目標インプレッション単価
目標インプレッション単価は、インプレッション数の最大化を目的とする入札戦略です。広告が1000回表示されるごとの平均費用を目標として設定します。設定された予算内で、出来るだけ多くのユーザーに広告を届けることを目的としています。そのため、ブランド認知の向上や新商品の周知など、広くリーチを取りたいキャンペーンに最適です。
目標インプレッション単価のメリット
ユニークリーチを最大化できる
目標インプレッション単価は、広告が1000回表示されるあたりの費用を基準に、できるだけ多くのユーザーに広告を届けるよう自動で最適化されます。そのため、ユニークリーチ(重複しないユーザーへの表示)を効率的に拡大できるのが特徴です。新規顧客への認知拡大を目的としたキャンペーンに適しています。
広告の表示位置を意識せず配信できる
クリックやコンバージョンではなく、広告の表示回数を重視するため、検索結果での順位や掲載位置にこだわる必要がなく、幅広い面で安定して広告を配信できます。表示機会を重視したいブランド認知やリーチ目的の施策に最適です。
目標インプレッション単価のデメリット
広告が見られていない可能性がある
広告が表示された回数を基に最適化されますが、実際にユーザーが広告をしっかり見ているとは限りません。スクロールで素早く通過された場合でも、インプレッションとしてカウントされるため、広告効果が薄い表示に対しても費用が発生する可能性があります。その結果、無駄な表示が増え、費用対効果が下がるリスクもあるのがデメリットです。
コンバージョン数の最大化
コンバージョン数の最大化は、設定した予算の範囲内で、Googleが自動的に入札額を調整し、できるだけ多くのコンバージョン獲得を目的とする入札戦略です。手動運用の場合、予算の使いすぎや逆に消化不足になるリスクがありますが、この戦略を使うことで効率的な配信が可能になります。広告費を最大限に活用したい場合に適した手法です。
コンバージョン数の最大化のメリット
手動調整の手間がいらない
コンバージョン数の最大化は、入札単価をGoogleが自動で最適化してくれるため、手動での調整が不要です。そのため、広告運用の経験が浅い人でも扱いやすく、設定や管理の手間を大幅に減らすことができます。日々の細かな入札作業に時間を取られず、効果的な運用が可能になります。
学習が進むと精度が向上する
コンバージョン数の最大化は、配信を続けることでユーザーの行動データが蓄積され、より効果的なターゲティングが可能になります。学習が進むにつれて、コンバージョンにつながりやすいユーザー層への配信精度が高まり、成果の安定化が期待できます。時間とともに最適化が進むため、継続的な運用に適した入札戦略です。
コンバージョン数の最大化のデメリット
十分なコンバージョンデータが必要
コンバージョン数の最大化を効果的に機能させるためには、過去のコンバージョンデータが一定以上蓄積されていることが前提となります。データが少ない状態では、配信の最適化がうまく行われず、成果が安定しない可能性があります。特に新規キャンペーンやアカウントでは、初期段階で期待通りのパフォーマンスが出にくい点に注意が必要です。
目標広告費用対効果
目標広告費用対効果は、設定した目標ROAS(広告費用対効果)に基づいて、Googleが自動で入札単価を調整してくれて、コンバージョン獲得を目的とする入札戦略です。広告費に対して、出来るだけ多くの売上やコンバージョンの価値を得られるよう最適化されるため、効率的な運用が可能です。特に、売上重視のECサイトや収益管理を重視する広告主に適しています。
目標広告費用対効果のメリット
売上重視のECサイトや有料サービスに最適
購入金額や契約金額にはばらつきがある商材でも、コンバージョンの価値に応じて自動で最適化されるのが特徴です。そのため、売上や収益性を重視するECサイトや有料サービスの広告運用に非常に適しています。価値の高いユーザーへの配信を優先できるため、効率的に収益を伸ばすことが可能です。
費用対効果を重視した運用ができる
あらかじめ設定した費用対効果を目標にして、Googleが自動で入札単価を調整します。これにより、広告費に対してできるだけ多くの売上や価値を獲得する運用が可能になります。限られた予算の中でも効率よく成果を出したい場合に適した入札戦略です。
目標広告費用対効果のデメリット
目標広告費用対効果が高すぎると配信が制限される
高く設定しすぎると、Googleのシステムが入札を控える傾向になり、広告が十分に表示されなくなる可能性があります。その結果、インプレッション数やクリック数が伸びず、配信ボリュームが極端に落ちることがあります。目標は実現可能な範囲で設定し、配信状況を見ながら調整することが重要です。
Google広告入札戦略を効果的に運用するために気を付ける、注意するポイント

入札戦略を効果的に運用するためには、いくつかの注意点や気を付けるべきポイントがあります。そこで今回は、手動入札と自動入札のそれぞれのポイントを説明していきます。
手動入札の4つのポイント
①入札調整に時間と手間がかかる
手動入札では、キーワードや広告グループごとに入札単価を個別に設定・調整する必要があります。そのため、扱うキーワードが増えるほど、管理にかかる時間と手間が大きくなります。特にキャンペーン規模が大きい場合、効率的な運用が難しくなる点に注意が必要です。
②市場の変動に即応しづらい
手動入札は、競合の入札状況や検索トレンドの変化に素早く対応するのが難しい点がデメリットです。状況に応じた調整が遅れると、広告の表示機会を逃す可能性があり、成果の低下につながることもあります。特に、市場の動きが激しい業界では注意が必要です。
③データ分析と調整の負担
手動入札で成果を出すには、定期的に広告のデータを分析し、入札単価を適切に見直す必要があります。そのためには、ある程度の専門知識と時間が必要となり、運用負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。特に広告効果を最大化したい場合には、細かな調整が欠かせません。
④拡張クリック単価の提供終了
2024年10月以降、Google広告では拡張クリック単価が廃止され、広告の配信は設定した入札単価のみに基づいて行われるようになります。これにより、コンバージョン率に応じた自動調整がなくなり、より精密な入札額の設定と管理が求められるようになります。運用の自由度が下がる一方で、手動での最適化スキルが重要です。
これらの点を踏まえて、手動入札戦略を採用する際は、目標や運用体制に合った適切な管理・調整の準備が欠かせません。リソースに余裕がない場合や細かな運用が難しい場合は、他の入札戦略も検討することが効果的です。
自動入札の5つのポイント
①学習期間中は成果が安定しにくい場合がある
自動入札は、過去のデータを活用して最適化が進む仕組みのため、配信開始直後は効果が安定せず、結果が出るまでに一定の時間がかかることがあります。数日から1〜2週間ほどの学習期間を想定し、初期段階では様子を見ながら運用を続けることが重要です。
②コンバージョンデータが少ないと効果が安定しにくい
自動入札は、過去のコンバージョン実績をもとに最適化されるため、データの蓄積が少ない新規アカウントや配信開始直後のキャンペーンでは、成果が出にくいことがあります。スムーズに運用するには、事前にある程度のコンバージョンデータを集めておくことが望ましいです。
③目標顧客獲得単価や目標広告費用対効果の設定値は現実的に
あまりに高い目標値にすると、Googleが入札を行いにくくなり、広告の配信機会が大きく減少する可能性があります。配信が極端に少なくなるのを防ぐためにも、まずは実現可能な数値からスタートし、運用状況を見ながら段階的に調整することが大切です。
④柔軟な調整がしづらい
自動入札では入札額の最適化をシステムが自動で行うため、キーワードやデバイス、配信時間帯ごとの入札を細かく調整することが難しくなります。そのため、細かな戦略設計や手動での微調整を重視する運用には不向きなケースもあります。
⑤パフォーマンス低下の要因が見えづらい
自動入札では、入札や配信がすべてシステムによって最適化されるため、成果が落ちた際に原因を特定するのが難しくなることがあります。どの要素が影響しているのか見えにくく、手動運用に比べて改善策を立てづらい場面もあります。そのため、定期的なモニタリングと過去データとの比較が重要です。
これらの点を踏まえ、コンバージョンタグやコンバージョン値が正しく設定されていないと、自動入札が正確に機能しません。導入前に必ず設定内を確認しておくことが重要です。また、自動入札にはそれぞれ特徴があり、向いている目的が異なります。コンバージョン数の増加、売上重視、クリック獲得など、自社の目標に合わせて最適な戦略を選びましょう。
Google広告入札戦略の使い分けのコツ
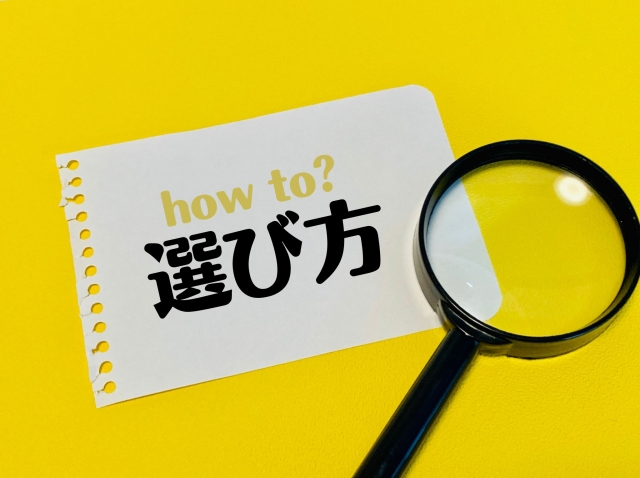
入札戦略を効果的に使い分けるためには、広告の目的、次期、予算などを総合的に考慮して最適な戦略を選択することが重要です。そこで、目的別、時期別、予算別の使い分けのポイントを説明します。
目的別の使い分け
・売上を伸ばしたい場合(コンバージョン重視)
商品の購入やサービスの申し込みなど、具体的な成果を増やしたい場合はコンバージョンを最大化する入札戦略が適しています。例えば「目標コンバージョン単価」や「コンバージョン数の最大化」を選択すると、設定した予算内でコンバージョン数を最大化するように入札が自動調整されます。
・サイトへの流入を増やしたい場合(クリック重視)
ウェブサイトの訪問者数を増やしたい場合は、クリック数を最大化する入札戦略が効果的です。「クリック数の最大化」を選択すると、設定した予算内で可能な限り多くのクリックを獲得するように入札が自動調整されます。
・サービスを広く知ってもらいたい場合(露出度重視)
ブランド認知度の向上を目的とする場合は、広告の表示回数や視認性を重視した入札戦略が適しています。「目標インプレッションシェア」や「視認範囲のインプレッション単価性」を選択すると、広告の表示頻度や位置を最適化できます。
時期別の使い分け
・キャンペーン開始直後
新しいキャンペーンを開始した直後は、まず広告の露出を増やすことが重要です。この段階では「目標インプレッションシェア」を設定し、検索結果の最上部や上部に広告が表示されるように調整すると効果的です。
・キャンペーンの安定期
キャンペーンが安定し、一定のデータが蓄積された段階ではコンバージョンを重視した戦略に切り替えるといいでしょう。「コンバージョン数の最大化」や「目標コンバージョン単価」を設定し、成果の最大化を図ります。
・季節性が影響する業界
季節やイベントにより需要が変動する業界では、定期的に入札戦略を見直すことが必要です。需要が高まる時期には積極的な入札を行い、閑散期には予算を抑えるなど、柔軟な調整が求められます。
予算別の使い分け
・予算が限られている場合
広告予算が限られている場合は、入札金額を調節して広告の表示頻度をコントロールすることが重要です。例えば「個別クリック単価性」を利用して、キーワードごとに入札単価を設定し、費用対効果を最適化します。
・十分な予算が確保できる場合
予算に余裕がある場合は、自動入札戦略を活用して効率的な運用を目指すことができます。「目標広告費用対効果」を設定し、広告費に対する収益を最大化するように入札を自動調整します。
まとめ
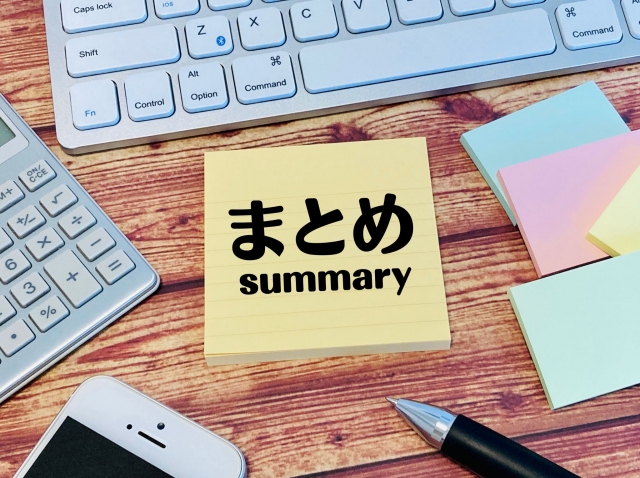
入札戦略は、主に手動入札と自動入札に分かれており様々な入札戦略があります。目的や時期によって使用する入札戦略が違います。どの入札戦略を使用するべきなのかをぜひ、こちらを参考にしていただければと思います。
また、弊社株式会社コアシーケンスでも、広告運用が可能ですのでぜひ、お問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
